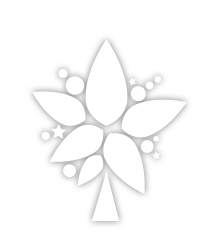はじめまして。
Satellite School MINANOHA@文京の鹿野 丈二(じょうじさん)です。#じょうじさん
MINANOHA@文京では、さまざまな遊びを体験することができます。遊びにはブームがあり、熱が冷めると止めてしまうゲームも多くあります。しかし、子どもたちのココロを長い間とらえて離さない遊びも存在します。その代表例がスライムです。
現代では、保育園などでスライム作りができるらしく、ぼくがMINANOHA@文京に勤めはじめたとき、スライムを手作りできると聞いて驚いた記憶があります。
スライムを作る材料は、基本的には、洗濯のり、ホウ砂に色をつけるための絵の具です。子どもたちは、それらの材料をボウルに入れ、スプーンや手を使って混ぜ合わせます。混ぜている間に、成長中のスライムは飛び散り、洋服はもとより、床やドアなどいろいろな場所に赤ちゃんスライムが付くことがあります。できあがったスライムを見て、触って、子どもたちは満面の笑みをうかべます。「どうだ!」とドヤ顔の子どももいます。何度も何度も見て、触って、ぐにゃぐにゃさせて、子どもたちは笑顔になります。

長い間、触られたスライムはやがて乾燥していきます。その過程で、ぼくはスライムをちぎって、おにぎりの形を作ってみました。米粒まで再現したそのおにぎりは、思いのほか上手にできあがりました。これをある子どもに渡すと、その子は、おにぎりが気に入ったようで、自分のかばんの中にしまって、家に持ち帰りました。おにぎりを手にして笑顔になった子どもの姿は印象深いものでした。


また別の日には、乾燥したスライムでシャウエッセンを作りました。その見た目のリアルさに子どもたちは驚き「うまそー。」と言ったり、それに触発されて目玉焼きを作った子どももいました。その子が作った目玉焼きの黄身は色鮮やかで、ぼくが作ったシャウエッセンを横に並べて朝食が完成しました。おとなが子どもに関わり、刺激をあたえることで、子どもには安心感とおとなへの信頼感が生まれます。また、おとなの影響を受けて、何かを作りだす経験は、子どもにとって自己表現の大切さを学ぶ機会となります。
このようにスライムには、手で触れる以外にも、目で見て楽しむこともできるのです。そんなスライムに子どもたちは魅了されるのです。そしてぼくにも、スライムに魅了された子ども時代がありました。
ぼくが初めてスライムと出合ったのは、小学生の頃でした。当時、発売されるや否やスライムは人気商品となり、おもちゃ屋さんでは予約しなければ購入することができませんでした。あれから何十年も経過しましたが、ぼくは今でも初めてスライムを触ったときの感触を思いだすことができます。
どうして、スライムがこれほど人気になったのか?それは、誰も今まで触ったことのない感触に心躍らされたからでしょう。その心踊る感触とは、冷たくひんやりとして、まるで宇宙からの未確認生物のように手のひらで自由自在に形を変えます。ずっと触っていたくなるくらい気持ちいい、手の平から伝わるその感覚は、何十年経過しても決して色あせない特別な感覚です。
この感覚を心理学的に考察しようと考えましたが、それはあまり意味がないことだと思いました。大事なことは、理論ではなく、純粋に「気持ちいい」という感覚、感情です。たとえるなら、2004年アテネオリンピックで金メダルを獲得した北島康介がインタビューで答えた「ちょー気持ちいい!」という感覚、感情です。
しかし、この感覚、感情を掘りさげるために文学作品を取りあげてみたいと思いますので、少しお付き合いください。近代の文豪、梶井基次郎の作品に「檸檬」という小説があります。年代によっては現代文の教科書に載っていたのでご存知の方もいると思います。この小説は、不安や抑圧を抱えた主人公がレモンを握ることで、その形状、色、温度、表面の感覚などから解放感や安心感を得るという物語です(結末については、ネタバレになるのでご自身で確認してください)。このレモンを握ったときの感覚とスライムを触ったときの感覚は、形や色は違っても、その本質は同じではないでしょうか。つまり、スライムにも解放感や安心感が得られる要素があると思うのです。ぼくは高校生の頃、この小説がとても好きでした。それはきっと、ぼくも主人公と同じように漠然とした将来に対する不安を抱えていたからだと思います。そんな不安を払拭してくれるレモンを僕は手に入れたいと思っていました。そして今、ぼくはレモンの代わりにスライムを作っている子どもたちを見守っています。
スライムには、人を癒す効果があると思います。ストレスにさらされているのはおとなだけではありません。その液体とも個体とも言いがたい物体が、子どもたちの自由な発想、創造力を引き出し、自己表現の手段となる。やがてそれが自信となり、そうした経験を積み重ねていくことが他者へのやさしさにつながっていく。ぼくはそう信じています。